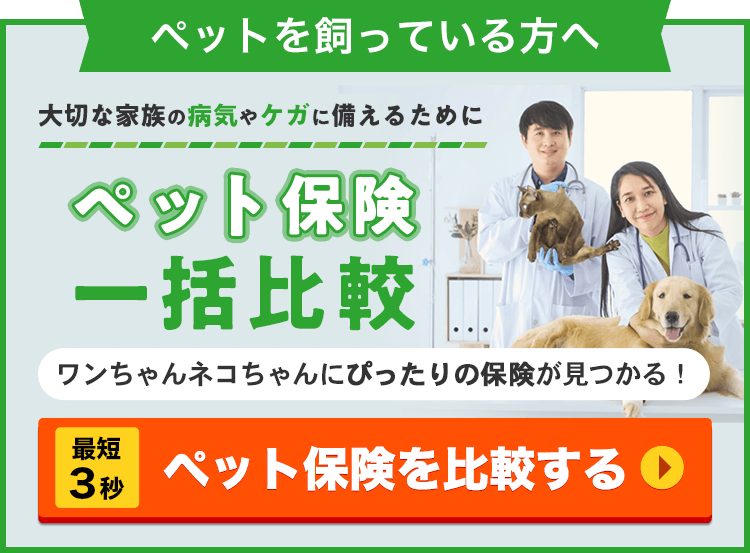愛犬がしつこく自分の足をペロペロとなめたり、ガジガジと噛んだりといった行動をとっている時があります。犬も猫のように体をきれいに保つためのグルーミングを行うと考えられていますが、猫ほどではないと考えられており、あまり頻繁に自分の足を舐めているようであれば皮膚病やストレスを抱えている恐れがあります。犬が自分の足をなめる理由にはどのような原因があるのか解説します。
目次
犬が自分の足をなめる理由
ストレス・暇つぶし
犬はストレスがあると足をなめたり自分の足を噛んだりする行動をして気持ちを落ち着かせようとしている場合があります。気持ちを落ち着かせるために自分の足をなめたり噛んだりする行動は犬のカーミングシグナルと呼ばれる行動の1つです。
犬のストレスの要因例
- お留守番の時間が長く飼い主とのコミュニケーション不足
- 散歩不足による運動不足
- 引越しなどによる環境の変化
- いたずらをして飼い主に強く怒られた
カーミングシグナル
カーミングシグナルとは、犬のボディランゲージであり、「Calm」と「Signal」が合わさった言葉です。「Calm」は「鎮める」や「落ち着いて」という意味があり、「Signal」は「合図」や「信号」といった意味があります。
足をなめたり噛んだりするカーミングシグナルの他にも犬が自分を落ち着かせようと行っている行動があるので、飼い主は愛犬のシグナルを注意深く観察し愛犬の気持ちを読み取ってあげる事で事前にトラブルを防止したり、愛犬との信頼関係を強めることも可能になるでしょう。
皮膚病・アレルギー
皮膚に異常があり、足をなめている可能性があります。例えば皮膚に痒みがありなめている場合で皮膚真菌症や脂漏症などが考えられます。また、指と指の間の皮膚に炎症が起きる指間炎でなめているという可能性もあります。
ノミやダニがついていたり、アレルギーによる痒みからなめていることも考えられます。主に皮膚病やアレルギーで愛犬が自分の足をなめている時は痒みが原因であることが多いです。犬が痒みでしつこくなめる事でなめた場所が湿った状態となり真菌も増殖しやすい環境となります。常にべたべたした状態で更に犬が痒みでなめてしまうという悪循環になる事も心配です。このような状態が見られたら動物病院で診察してもらいましょう。
【皮膚病の例】
- 皮膚真菌症
- 脂漏症
- 指間炎
ケガややけど
ケガややけどなどで足をなめている場合もあります。ケガややけどなどを負っていると痛みが原因でなめていると考えられます。歩き方に異常が見られたり、出血をしていたりといったことがあれば早めに動物病院を受診しましょう。犬はケガややけどなどで気になる箇所がある場合、痛みの緩和に自分でなめ続ける場合があります。自分の皮膚をなめ続けると皮膚炎や脱毛など別の炎症の心配もあるため、早めに動物病院を受診しましょう。
【よくある犬の足のケガの例】
- 打撲
- 捻挫
- 爪が割れた
- 肉球のケガ(とげが刺さっている、擦り傷があるなど)
骨や関節の異常
上記のケガややけどを負っているため足をなめている様子と同じく、骨や関節に異常がある場合にも痛みやいつもとは違う違和感で自分の足をなめている場合があります。骨や関節の異常がある場合、放置が長引くと歩行が困難になったり、悪化の恐れも心配です。ですから、この場合も早めの動物病院への受診が大切です。
【よくある犬の骨や関節の異常の例】
- 関節炎
- 関節リウマチ
- 骨折
愛犬が足をなめたり噛んだりするのをやめさせるには?
愛犬が足をなめてり噛んだりする行動にはいくつかの原因があることが分かりました。足をしつこく舐める行動はなめることによってその場所に脱毛の心配や炎症を引き起こすといった二次被害の心配もあります。なめている原因によって対処法や予防法を知っておきましょう。
ストレス・暇つぶしが原因の場合
ストレスや暇つぶしが原因で足をなめている場合は、愛犬のストレスを取り除いてあげる事が一番の予防になります。犬は人が考える以上に繊細な動物で環境の変化などを敏感に感じ取ります。飼い主との信頼関係の構築が犬の精神状態には重要です。犬もそれぞれ性格が異なりますから、愛犬の性格をよく理解し、ストレスのない環境を作ってあげる事が大切です。適度な運動、飼い主とのコミュニケーションはとても大切です。お留守番が長くケージの中にいる時間が長いといった環境の場合は、おもちゃを与えたり、愛犬が足をなめて暇つぶしをすることがないように工夫してあげるように対策しましょう。
アレルギーが原因の場合
アレルギーが原因で痒みがあり、足をなめている場合は、アレルギーのある物質を避ける事が一番の予防法になります。アトピー性のアレルギー症状がある場合は足の指の間などに痒み等の症状が出る事が多いです。
犬も人と同じくダニやほこり(ハウスダスト)、花粉、特定の食べ物などにアレルギーを持つ犬がいます。何らかの環境中のアレルゲン(抗原)に対する過剰な免疫反応で皮膚に症状が現れる場合がありますので、アレルギーのある犬は、何に反応しているのか、アレルギー物質を特定し避ける事が重要になってきます。
-

犬の皮膚病はどんな病気?愛犬を皮膚トラブルから予防しよう!
犬の皮膚病は動物病院への受診数も多く、犬がかかりやすい代表的な病気のひとつです。皮膚病による痒みや脱毛に悩まされている犬や飼い主は多いです。犬の皮膚病とは一体ど ...
ケガや関節炎などの異常が原因の場合
ケガや関節炎など身体的な要因が原因の場合は、愛犬がケガをしないように気を付けたり、乾燥の予防や年齢に応じたケアなどでケガをしないように飼い主が気を付ける事が大切です。しかし、気を付けていてもケガをしてしまう時があります。犬は痛みや違和感を言葉で伝える事ができません。歩き方に普段とは違う異常を感じたり、急に足を気にしてなめているような行動があれば早めに動物病院を診察してもらいましょう。
犬の医療費とペット保険
犬が自分の足をなめたり噛んだりする理由には、ストレスが原因の場合や足に異常がある場合があります。ケガなどが原因で足をなめているような場合には早期に動物病院を受診し適切な治療を行う必要があります。その場合には思わぬ医療費がかかってしまうかもしれません。また、ストレスなどでなめている場合でもなめる事が癖になり、舐めることで炎症を引き起こしてしまう場合も多いです。そのような時にも動物病院を受診し適切な治療で治してあげる必要があります。
犬の医療費は、かかった費用を全額飼い主が負担します。犬には人間のような公的医療保険制度がないため、愛犬が動物病院で治療を受けたり、通院が必要になったりした場合、その治療費や薬代は飼い主が全額自己負担で支払います。骨折などで長期にわたり通院が必要になる場合などでは、通院で多額の出費が必要となったというケースや手術が必要な場合でも高額な手術費用が必要となる場合も多いです。
そのような場合に備えために、ペットが病気やケガで治療を受けた場合にかかった費用を限度額や一定割合の範囲で補償するペット保険に加入するという人が増えています。ペット保険に加入していれば、一定の費用については保険から補償が受けられるため急なペットの体調不良でも医療費負担を軽減することができます。犬の関節炎の発症は高齢の犬に多いです。ペット保険は民間の保険会社が販売しているものなので、加入に条件が設けられおり、ペット保険の加入条件は7歳から8歳で設けられていることが多く高齢の犬の動物病院の通院費のためにペット保険に加入しようと思っても既に加入できない場合もあります。ですから、突然のペットの体調不良やケガなどによる医療費に備えるためには愛犬が若いうちにペット保険の加入を検討しておくとよいでしょう。
-
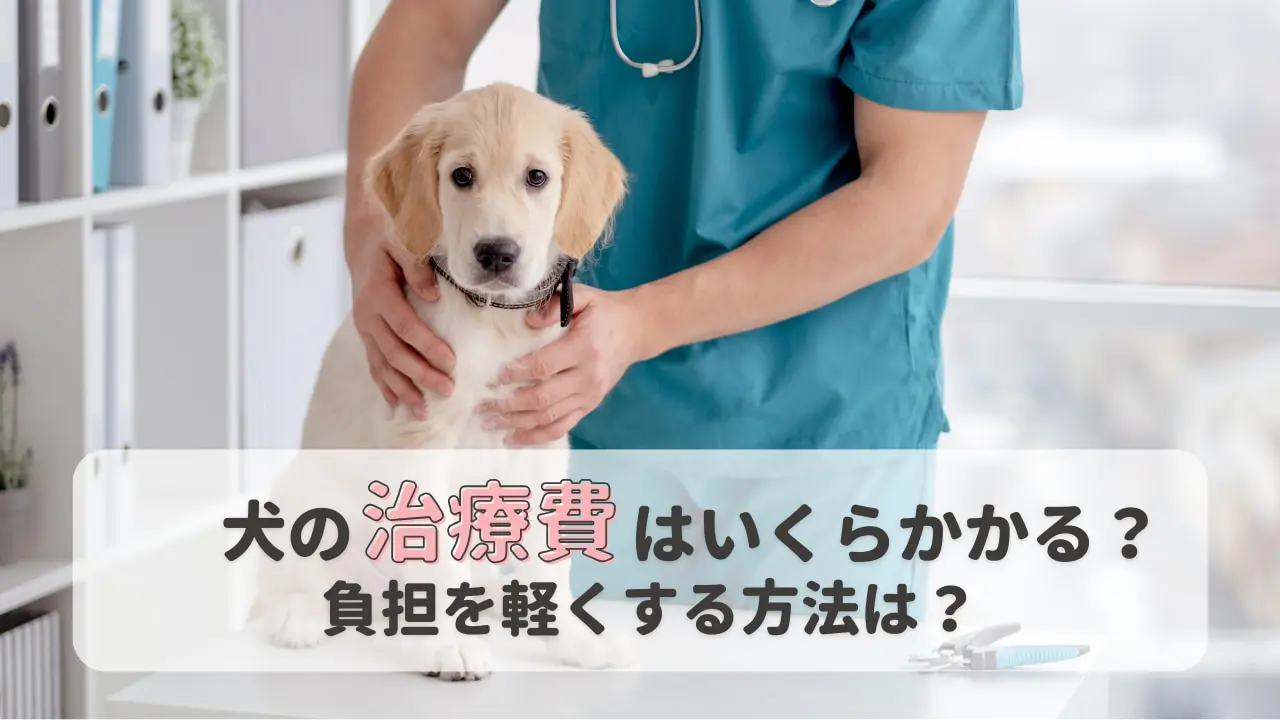
犬の治療費はいくらかかる?負担を軽くする方法は?
犬を飼っていると思わぬケガや病気で治療が必要となることがあります。そうした場合、どれくらいの治療費がかかるのでしょうか。また、高額な治療費がかかった場合、その負 ...