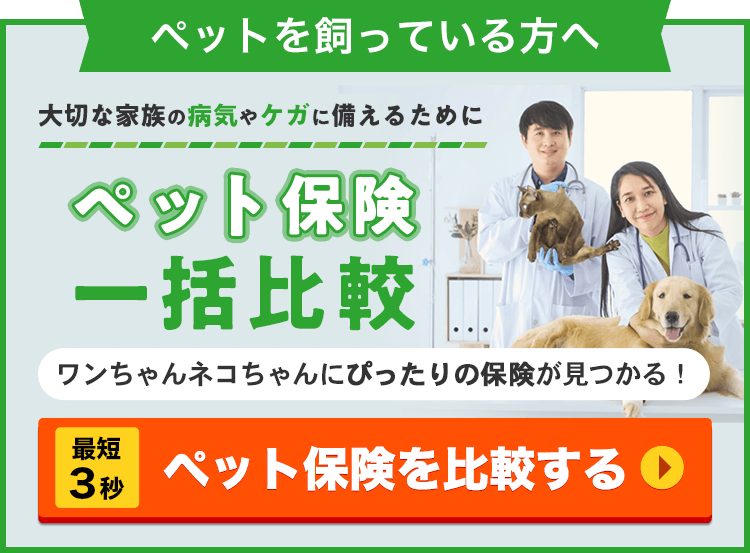愛猫が頭を振っていたり耳をあしで掻いていたりして、かゆがっている様子がみられたら外耳炎かもしれません。外耳炎は再発することも多く、きちんと症状の原因を把握することも重要です。視力が悪い猫にとって耳は物の位置や距離を把握する大事な器官です。愛猫に元気に過ごしてもらうためにも、耳のケアで病気を予防していきましょう。
猫の外耳炎とは
猫の外耳炎とは、耳の外耳(がいじ)に炎症が起こる病気です。猫の耳は外耳(がいじ)・中耳(ちゅうじ)・内耳(ないじ)とあり、耳の外耳の部分にあたる耳の穴から鼓膜までの間に炎症が起こります。炎症が起こる原因としては、寄生虫(耳ダニなど)、細菌や真菌(カビ)などの繁殖、アトピー性皮膚炎や食物アレルギー、異物混入や腫瘍などがあります。
外耳炎の症状について
猫が外耳炎になると、耳から臭いにおいがしたり赤く腫れたりします。猫自身も耳を掻く仕草や頭を振る行動をとります。さらに悪化すると耳の奥に炎症が広がってしまい、中耳炎や内耳炎になることもありますので、以下のような気になる様子があったら早めに動物病院を受診しましょう。
- 頭を振る
- 耳を掻く
- 耳垢が増える
- 耳の中が赤く腫れる
- 耳から悪臭がする
外耳炎の原因について
外耳道は鼓膜までつながっていますが、耳の自浄作用があるため耳の中の汚れは自然に奥から外に排出される仕組みになっています。しかし、耳の中が腫れて耳道が狭くなる等、耳道の通気性が悪く自浄作用が働かなくなってしまうと、細菌や真菌が増殖しやすい環境となるのです。
寄生虫等が原因の場合は駆虫薬を使って根治させることができますが、アトピー性皮膚炎や食物アレルギーが原因の場合は炎症した部分を治すだけでなく根本的な原因を治療しなければ再発してしまいます。そのため、動物病院で検査等をしてもらい、原因を突き止めたうえで治療する必要があるのです。

主な外耳炎の原因
寄生虫が原因のケース
- ミミヒゼンダニ(耳ダニ)
- ニキビダニ
- マダニ
ミミヒゼンダニ(耳ダニ)は、大量の黒っぽい耳垢が出る状況となり強い痒みと痛みを伴い、特に子猫や外飼いの猫がかかりやすい傾向にあるといわれています。ダニに感染すると痒みや痛みにより猫が耳の違和感を気にして掻くようになり、外耳にひっかき傷ができることもあります。傷ができると更に細菌・真菌の増殖原因となり外耳炎が悪化してしまいます。
細菌・真菌(カビ)が原因のケース
- マラセチア感染
- ブドウ球菌
外耳に細菌や真菌が増殖すると耳から独特の臭いにおいがします。猫の耳には自浄作用があり、耳の掃除をしなくても耳の奥の汚れが外へ出るようになっています。耳に傷ができたり耳の中の湿度が高くなったりすると皮膚のそうした機能が働かなくなってしまい、耳の中に細菌や真菌が増殖し外耳炎を引き起こすことがあるのです。
アレルギーが原因のケース
- アトピー性皮膚炎
- 食物アレルギー
アトピー性皮膚炎や食物アレルギーのある猫も外耳炎になることがあるため注意が必要です。皮膚のかゆみにより耳を搔いてしまい、腫れた耳道に細菌などが感染することで外耳炎を発症することがあります。
異物が原因のケース
- 異物の混入
外に出入りをする猫の場合は、草の実などが耳に入ってしまい気付かずに放置してしまったことで外耳炎を発症してしまったというケースもあるようです。
その他
- 腫瘍
- 体質によるもの
- 綿棒などによる誤ったケアが原因の場合 など
治療法について
外耳炎になってしまうと自然に治ることは難しいため、動物病院を受診し適切な治療を受けましょう。耳の中や耳垢に原因となる寄生虫や細菌等がいるかを確認し、耳を洗浄して点耳薬や投薬で治療をおこなうことが多いようです。
耳状態の確認
耳鏡や耳の内視鏡を使って耳の中の状態を確認します。耳垢の量や大きさ、炎症の程度や範囲などをみます。耳垢があった場合は顕微鏡を使って寄生虫や細菌がいるかを確認し、外耳炎の原因を特定します。
耳洗浄
耳の中の汚れや耳垢を落とすために耳を洗浄します。
点耳薬
痒みや炎症を抑える点耳薬を投与します。
駆虫薬
寄生虫が原因の場合は、寄生虫を駆除する薬を投与します。他の猫にもうつる可能性があるため、多頭飼いの場合は寄生虫の感染に注意しましょう。
アレルギーの治療
食物アレルギーに対する治療をおこないます。
どんな猫が外耳炎になりやすい?
スコティッシュフォールドなどの折れ耳の猫は耳の中が確認しづらいため、耳垢が溜まりやすく耳の異常に気付きにくい傾向があります。耳の脂分が多い猫は、分泌物も耳垢も多く溜まりやすい体質のため注意が必要です。
外耳炎はどうやって予防する?

耳を清潔にする
日常的に耳をケアして清潔に保つことも有効な予防方法です。人間と同じようについ綿棒を使いたくなってしまいますが、デリケートな耳の中を傷つけてしまう可能性があるため綿棒の使用はやめましょう。
家で耳掃除をする場合は水で湿らせたコットンやガーゼを使い、表面を優しく拭いてあげましょう。一週間に一度が目安ですが、特に汚れがなければ耳を拭く必要はありません。また、耳から悪臭がしないか、かゆがっていないかなど日頃から様子を気にかけることも予防につながります。
屋外に出た時は注意する
室内飼いの猫に比べて、外に出入りする猫はダニなどに感染する機会が多くなります。また、植物の種などが耳に入り込むこともありますので、外から戻ってきた時にはこういった物が付着していないか確認してあげましょう。
まとめ
一口に外耳炎といっても、その原因はダニや細菌感染などさまざまです。原因によってはかゆみが激しい場合があります。自分の耳を掻いて傷がついてしまうとさらに悪化してしまう可能性がありますので、早めに動物病院を受診しましょう。
特に湿気が多い梅雨の時期から夏にかけては耳の中の湿度も高くなりやすいです。湿度が高くなると細菌や真菌が繁殖しやすくなるので外耳炎に注意しましょう。
もし外耳炎にかかってしまった場合、治療費はどのくらい必要になるのでしょうか?
外耳炎の状態や検査内容によって異なりますが、軽度な外耳炎であれば2,000円~3,000円程度の費用で治療を受けられるようです。再診が必要だったり、重度の症状で手術が必要になったりする場合は医療費も高くなります。なお、動物医療での治療費は各動物病院で設定されており、同じ治療を受けていても病院によって医療費が異なることもあります。
外耳炎は放置していても治らず、悪化してしまうこともあります。ペット保険に加入していれば、医療費を気にせずにすぐに動物病院を受診することができ、早期発見・早期治療に繋げられます。
ペット保険とは
ペット保険は、ペットが病気やケガで治療を受けた場合にかかった費用を限度額や一定割合の範囲で補償する保険です。一定の限度額以内であれば保険対象の治療費の100%を補償するというプランもありますが、多くのペット保険では治療の70%や50%を補償するという形になっています。さらに、ペット保険は基本補償である「通院補償」「入院補償」「手術補償」の組み合わせで選択し加入します。愛猫に病気やケガの疑いがあった時に医療費を心配することなく早期に動物病院へ向かえるようにペット保険で備えていきたいですね。
外耳炎の原因によっては長期間の通院や手術が必要になることもあり、治療費が数万円、数十万円とかかってしまうこともあり得ます。急な出費に耐えられるような収入や貯蓄があれば問題ありませんが、そうでないのであればペット保険で備えることも検討しておくとよいでしょう。