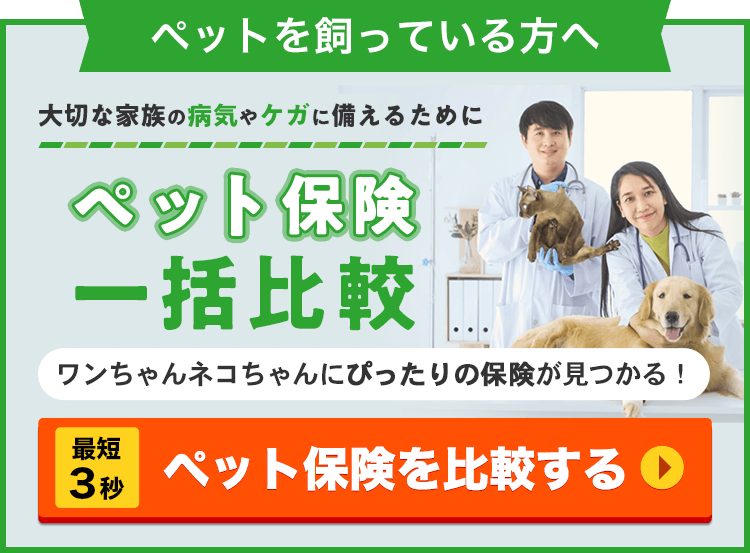保護犬や保護猫をお迎えする時には、ケガや病気になった場合に備えてペット保険への加入を検討しましょう。しかし、保護犬や保護猫は年齢や正確な生年月日が分からないことが多く、そのままでは保険に入ることができません。加入の前にどんなことをすればいいのでしょうか。
保護犬・保護猫もペット保険に加入できる
里親として保護犬や保護猫を迎え入れる場合や、知り合いから犬や猫を譲り受ける場合でもペット保険に加入することができます。
ペット保険に入る際には、生年月日や体重、今までにかかった病気や治療歴などを知らせる必要があります。過去に保護されていたかどうかは関係ないため、ペットショップやブリーダーなどから購入した場合と同じように加入できます。
年齢や生年月日が分からない時は?
保護犬や保護猫は、正確な年齢や生年月日、生まれつきの病気等情報が分からないことが多いです。そんな時は動物病院で年齢を推定してもらいましょう。
獣医師が歯や毛並み等の状態からどのくらいの年齢かを推定してくれます。ペット保険に申し込む際は年齢のほかに生年月日も必要になります。正確な日付がわからない場合には、自宅に迎え入れた日や推定された月の1日を生年月日として記入することが多いようです。保険会社によって対応が異なるため、詳しくは申し込み先の保険会社へ確認しておきましょう。
動物病院で健康状態も確認する
動物病院で推定年齢を出してもらうのと合わせて、保護犬や保護猫の健康状態も確認してもらいましょう。
ペット保険に申し込む際には既往歴や過去の治療歴、ワクチンの接種状況なども申告する必要があります。健康状態が分からない場合は加入を断られてしまうケースもあるため、生まれつきの病気や、保護される前に受けたケガや治療歴等を知っておきましょう。
保護団体から譲渡された場合は予防接種を受けていることが多いですが、未接種のこともあります。予防接種で防げる病気はペット保険では補償対象外となるため、事前に接種しておくと安心ですね。
動物は具合の悪いところを言葉で伝えることができません。もしペット保険に加入しなかったとしても、これから一緒に生活するうえで健康状態を知っておくことが重要です。生まれつきの病気やかかりやすい病気を把握しておけば、体調の異変に気付いて病気の早期発見・早期治療につなげることができます。
ペット保険に加入できないケースは?

ペット保険に加入する際には「告知事項」を保険会社に知らせる必要があります。告知内容によっては条件付きで加入する場合や、加入を断られてしまう場合がありますので解説します。
高齢の場合
保護犬や保護猫をお迎えする時に既に高齢になっていることがあるかもしれません。年齢が高くなると病気になるリスクも増えるため、7歳~8歳を超えると加入しづらくなってしまいます。中には10歳以上でも入れるペット保険もありますが、若い年齢に比べると保険料が高くなることやシニア期にかかりやすい病気が補償されないことがあります。高齢になってから加入する場合は補償内容と保険料のバランスに注意しましょう。
病気やケガがある場合
先天性の病気や過去半年以内にかかった病気、治療中の病気やケガがある場合は加入を断られてしまうことがあります。特に糖尿病や腎不全、悪性腫瘍などの病気をもっている場合は入れない可能性が高くなります。
すべての病気やケガに当てはまる訳ではなく、病気の種類によっては完治すれば加入できる場合や、特定の病気や部位だけ補償対象外にする条件付きで加入できる場合もあります。例えば緑内障で特定部位(目)が不担保になったとしたら、目が原因の手術や入院は保険金が支払われませんが、それ以外の病気やケガは補償されます。なお、保険会社によって対象になる病気は違ってきますので、加入の前にきちんと確認しましょう。
病気を隠すのはNG!
加入しにくくなるからといって病気を隠して申し込むのは告知義務違反となります。もし告知をせずに保険に加入すると、保険金が支払われない場合や契約自体が解除される場合があります。もちろんこれまで払ってきた保険料も戻ってきません。保険会社への告知は嘘をつかずに正しく行うようにしましょう。
加入を断られたら
告知事項や条件は保険会社によって異なります。同じ病気でも、A社では断られたもののB社では加入できるケースもあります。ペット保険を検討する際には様々な保険会社を比べることで、愛犬や愛猫に合った保険を選んでいきましょう。ペット保険を比較する際には、犬は年齢と体重、猫は年齢が分かっていれば大丈夫です。簡単に保険料や保障内容を比べることができるのでぜひ利用してみてください。
まとめ
保護犬や保護猫でもペット保険に申し込むことができます。申し込みには生年月日や年齢が必要ですが、分からない場合は動物病院で年齢を推定してもらいましょう。ただし、年齢制限や健康状態などによって契約できないこともあるので注意しましょう。保険会社によって告知事項は異なるため、加入を断られてしまっても他のペット保険なら契約できることもあります。根気強く探してみましょう。
犬や猫には公的保険がないので治療費は全額飼い主負担となってしまいます。保護猫や保護犬は保護される前にどのような環境で育ったかというような情報をはっきりと知ることはできません。元気に健康で過ごしてもらうためにも、病気に対してペット保険で備えておいた方がよいでしょう。