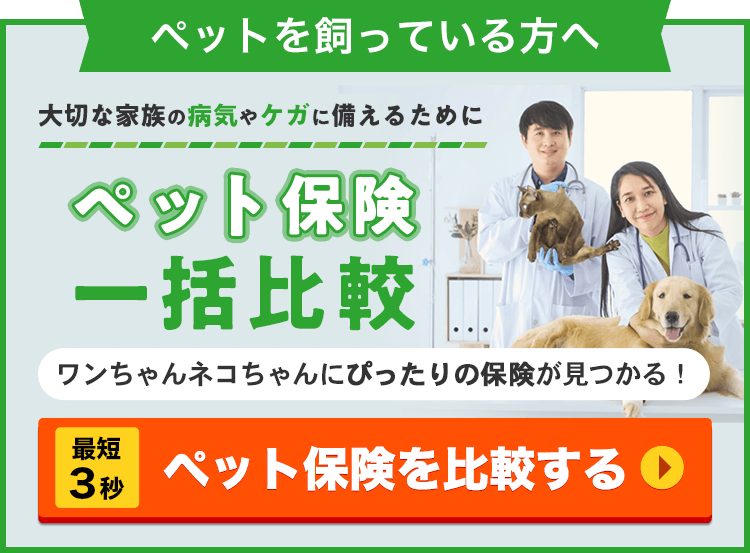一般財団法人ペットフード協会の全国犬猫飼育実態調査によると、2020年度は2019年よりも犬や猫などのペットの飼育を開始した人が増加しており、過去5年間の中でも伸び率、飼育頭数ともに最も多かったようです。2020年は新型コロナウイルス感染症の流行による外出制限で在宅時間が増えたことによりペットに癒しや安らぎを求める人が増えているという背景もありそうです。ペット飼育者の増加と共にペット保険加入者も増えているようですが、ペット保険加入のメリットとデメリットをまとめておきましょう。
目次
ペット保険のメリット
犬や猫などのペットも生き物ですから、ケガをしたり病気になってしまう事もあります。日本には、動物病院もたくさんあり、ペットを飼育している人はペットがケガをしたり、調子が悪そうなときには動物病院で獣医師に治療をしてもらいます。具合が悪そうなペットを病院に連れてくという行動は、飼い主が判断し行いますが、それは、人が調子が悪い時に病院に行くという感覚と変わらないでしょう。しかし、人と違う点は、ペットは家族ですが人のような健康保険制度がないため必要となった医療費は全額飼い主が負担するという点です。ペット保険は飼い主がペットに必要になるかもしれない医療費の軽減のために加入する保険になります。
メリット1:医療費・高額な治療費をカバー
ペット保険に加入するメリットとして一番大きいのは、今は健康なペットでも、ケガや病気をしてしまうリスクがあり、高額な医療費が必要になった時にペット保険で医療費を軽減することができるという点です。ペットの医療費は飼い主が全額負担しなければいけないため、飼い主にとっては大きな出費となってしまいます。費用面の心配から可愛がっているペットに受けさせてあげられるはずの医療を断念せざるを得ないような状況になることは飼い主にとっても辛いものです。現代の社会では特に犬や猫などのペットは家族として生活を共にし暮らしていることが多いです。そのようなペットがケガをしたり、病気を患ってしまった時、高額な医療費がかかってもペット保険で飼い主の医療費負担を減らすことができるのがペット保険です。ペット保険は、人の健康保険のような役割を果たすことができるという点がペット保険のメリットとして大きいでしょう。
「診療費の安さ」を動物病院選定の基準にする人も多い
日本獣医師会が発表する「家庭飼育動物(犬・猫)の飼育者意識調査(平成27年度)」によると、動物病院を選ぶ選定基準に最も重視するポイントとして診療費の安さを選択する飼い主も一定数いるようです。動物病院の医療費は、各病院の設定で決められています。ペットの医療費を気にしているという飼い主も多いようですので、ペットの医療費が心配な人は、万が一大きなケガや病気などで高額な医療費が必要になっても医療費の心配なく最善の医療を受けさせてあげられるようにペット保険で備えておくという方法があることを知っておきましょう。
参考:日本獣医師協会「家庭飼育動物(犬・猫)の飼育者意識調査(平成27年度)」
メリット2:ケガ・病気の早期発見、早期治療ができる
ペットの具合が悪そうな時、飼い主が異変を感じていても医療費を心配して動物病院を受診することをためらってしまったために治療が先延ばしになり適切な医療を受けさせてあげられなかった、などというケースもあるでしょう。ペット保険に加入しているという事は飼い主のそういった心理的な負担も軽減してくれることがあります。ペット保険に加入していることでペットの医療費に関する負担が軽減されているという安心感は、医療費の心配をせずに早期に病院を受診することに繋がり、病気の早期発見、早期治療が可能になります。病気を早期に発見し、治療ができれば早期回復となることが多いです。大切なペットがケガや病気に耐える辛い期間や治療期間も短くできます。ペットの医療費の負担が家計への負担にならないようにペットも家族も安定して幸せに暮らせるような状況を作っておくことにもペット保険は役立つことがあります。
メリット3:損害賠償に備える(特約)
ペット保険は、メインとなるペットの治療費の補償に加えて、ペット賠償責任特約を追加で契約することができる場合があります。ペット賠償責任特約とは、ペットが他人にケガをさせたり他人のモノに損害を与えて法的な損害賠償責任を負った際に保険金が支払われる保険です。飼い犬が散歩中に他人にかみついてケガをさせてしまったという場合やペット同士がケンカをしてケガをさせてしまったようなケース、ペットを連れて他人の家に遊びに行ったときにペットが家のものを壊してしまったような場合などに損害賠償費用などを補償してもらえます。保険金額(保険金の上限額)は数百万円~1000万円ということが多いです。保険会社が示談交渉をしてくれるというサービスがついていることもあるようです。
犬などは躾をしっかり行っていても思わぬトラブルを起こしてしまう場合があります。また、躾などが難しい種類のペットも多くいます。そのような場合にペット賠償責任の契約があると安心です。
自動車保険や火災保険で既に備えられている場合がある
ペット賠償責任特約の注意点としては、自動車保険や火災保険の特約にある個人賠償責任特約や日常賠償責任特約と補償内容が重複するということです。しかも、自動車保険や火災保険の特約ではペットによる損害に限らず、自転車の事故で損害を与えてしまった場合や水漏れでマンションの階下の部屋に損害を与えてしまった場合なども補償の対象となります。また、保険金額もペット賠償責任特約よりも大きくなっています。さらには保険会社が示談交渉を行ってくれる示談交渉代行サービスもついていることが多いです。
すでに自動車保険や火災保険の特約で個人賠償責任特約や日常賠償責任特約を契約している場合、ペット保険でペット賠償責任特約を契約する必要はありません。重複して契約しても二重、三重に保険金を受け取れるというわけではなく、実際の損害額までしか受け取れないのです。したがって、すでに個人賠償責任特約や日常賠償責任特約を契約しているのであれば、ペット賠償責任特約を契約することは保険料の無駄払いとなってしまうため、ペット保険のペット賠償責任に特約に契約する前に既に損害賠償責任に契約していないか確認してみましょう。
ペット保険のデメリット
ペット保険は、ペットが将来、ケガや病気で治療した医療費に備えるための保険です。現在、健康なペットに必要になるかどうか分からない医療費のための保険料を支払うことになります。さらに、ペット保険は掛け捨ての保険なので、ペット保険を利用しなければ支払った保険料は無駄になってしまいます。ペット保険の注意事項をデメリットとして紹介していきます。保険金が受け取れると思っていたのに補償対象外だった、といいうトラブルがないように注意しましょう。
デメリット1:すべての医療費が補償されるわけではない
ペット保険の基本補償は、ペットの病気やケガの治療による通院・手術・入院でかかった医療費の補償です。「通院補償」「入院補償」「手術補償」の基本補償から必要な補償の組み合わせを選択し、決められた補償割合で支払った医療費の補償を受けます。医療費は加入時に決めた補償割合で治療費の何%を保険金として受け取るかが決まるため自己負担分も発生します。「保険に加入したのだから動物病院に支払う費用全てが補償対象」となると思い込んでいる人もいるかもしれません。ペット保険の保険金請求で支払われると思っていた医療費が支払われなかったというようなトラブルにならないようにペット保険のパンフレットや重要事項説明書などをしっかり理解した上で加入ましょう。
支払限度額、免責金額に注意
ペット保険には、通院や入院1日あたりに支払われる保険金や手術1回あたりに支払われる保険金、年間の合計の保険金に限度額が設定されていることが多くあります。保険金は支払限度額の範囲内で支払われることになるため加入するペット保険がどのように設定されているか確認しておきましょう。
また、免責金額の設定がある場合もあります。免責金額は、その設定された金額の分は自己負担しなければいけません。免責金額が設定されていれば、かかった医療費から設定された免責金額を差し引いて保険金の補償割合が計算されることになります。免責金額が5,000円で設定されている場合において、医療費が5,000円以下であれば保険金は支払われず、医療費が15,000円となったケースを例にしても(15,000円-5,000円)×補償割合のように計算されます(保険会社によって計算方法が異なる場合があります)。免責金額が設定されている場合、保険料が安いという特徴がありますが「保険金が支払われなかった、減らされた」と勘違いがないように補償内容を理解してペット保険を選択する必要があります。
事前にわかっている先天性疾患、既往症は補償対象外
先天性の疾患があり、医療費がかかる、ケガをしてしまったため医療費を軽減したい、とペット保険の加入を考えてもペット保険では加入前に発覚している先天性疾患や医療費は補償対象外となります。あくまでもペットが将来、かかってしまうかもしれない医療費負担に備える保険のため事前にわかっているケガや病気は補償対象外となります。ペット保険加入後に発覚した先天性疾患の対応は、加入するペット保険の対応によります。保険会社によっては当該保険期間内は補償を受けることができても、翌年度の契約から補償対象外となるなど対応はそれぞれなようです。いずれにしても、後々トラブルとならないように先天性の病気が発覚したら正確に情報を保険会社に報告しましょう。
デメリット2:予防費用や予防できる病気、避妊、去勢費用は補償対象外
犬や猫などのペットは特にワクチンの接種により予防できる病気があります。ワクチン接種などの予防費用はペット保険の補償対象外となります。ただし、飼い主としてペットの健康状態を維持するためにワクチンによる感染症の予防などのケアは大切なことです。そのため、ペットがワクチン接種によって予防できる病気にかかってしまった時の医療費も一部の場合(※)を除き、ペット保険の補償対象外となります。ペット保険に加入する際のパンフレットや重要事項説明書などで補償対象外となるワクチン等の接種によりペット保険の補償対象外となる予防できる病気の確認をしておくようにしましょう。
また、去勢手術や避妊手術にかかる費用もペット保険の補償対象外となっています。去勢・避妊手術は健康体に施す処置であり、こちらも病気やケガの治療には当たらないため補償の対象とはなりません。なお、他の傷病の治療のために去勢・避妊手術を行ったという場合には補償対象となることもあります。健康を維持するための費用は補償対象外ですから、健康診断費用なども補償対象外です。
※獣医師の指導により予防ワクチン接種などの処置が講じられていても発症した場合や獣医師の判断により予防措置を講じる事が出来なかったと認められる場合
デメリット3:ペットの年齢制限と保険料の値上がり
ペット保険は加入に年齢制限が設けられていることが多く1年更新で契約を更新していくことがほとんどです。更新は終身でできるという保険会社が多いですが、更新できる年齢に上限がある保険会社もあります。ペットが若い時に加入していれば、加入時の保険料で更新し続けられるかというと、そういうわけではなく、1年更新でペットの年齢が上がれば保険料も高くなることが多いです。では、ペットが高齢になり、ケガや病気をしてしまうリスクがたかくなってから加入しようと考える人もいますが、ペット保険は新規加入の年齢制限を7歳前後で設定されていることが多く、医療費がかさむ年齢になってからペット保険の加入を考えても加入が難しく加入できる保険会社の選択肢が限られるといった点があります。このように、ペット保険はペットに異常がなく健康な時に加入するものである、保険料は1年更新で年齢が高くなれば保険料も高くなる、年齢制限があるため高齢になってからでは加入が難しい、などといった点がペット保険の加入有無について飼い主を悩ませる点でもあるでしょう。
ペット保険を選ぶときのポイント
ペット保険とはどういうものか、メリットやデメリットを押さえてペットを家族として迎えたらペット保険の加入について家族で相談してみるとよいでしょう。では、ペット保険に加入する際、どのようなことを意識して選べばよいかポイントを紹介します。
ポイント1:補償プランの選択
ペット保険の補償プランは、通院・入院・手術をフルカバーするタイプか、通院のみ、もしくは入院・手術特化のプランがあります。ペットによってかかりやすい病気やケガは違います。そのため必要な医療サービスも変わってきます。補償プランを選ぶ際には、そのプランがペットのかかりやすい病気やケガのカバーをしているかどうか、これらを重視して選びましょう
| ①通院費用の補償 | 病気やケガなどにより獣医師の診察を受けた場合の診療費用・処置費・処方薬代など ※薬の処方代は、治療が目的の場合に補償対象となります。 |
|---|---|
| ②入院費用の補償 | 病気やケガなどにより入院にかかった医療費用 |
| ③手術費用の補償 | 病気やケガで手術をしたときにかかった医療費用 |
ポイント2:補償割合を選ぶ・支払い限度額、免責金額の確認
既に説明した通り、ペット保険は、補償割合を選択してどの商品に申し込むかを選択します。ペットがかかった医療費に対してどのくらいの補償割合で保険金が受け取れれば安心か、支払い限度額や免責金額を確認し納得したうえで商品を選びましょう。補償割合などは当然、補償割合が大きいほど保険料は高くなります。補償内容と保険料のバランスで保険料が家計の負担にならないように設定することも大切です。
ポイント3:保険金の請求方法
ペット保険の保険金請求方法には後日請求と窓口清算の二種類があります。後日請求の場合、診察後の支払いは自費で払い、後日保険会社に保険金を請求します。窓口清算の場合、保険金が支払われる分を除いた治療費を払えばよいので、余計な手間をとる必要がありません。動物病院と契約する保険会社が窓口清算に対応しているかどうかというところもポイントになります。かかりつけの動物病院がどのような対応になっているか確認してみるとよいでしょう。
ポイント4:付帯サービスや割引
ペット保険にも様々な特約やサービスをつけることが可能です。ペットの健康状態や自分のお財布事情にあった特約やサービスを検討してみましょう。
| 特約やサービス名 | 内容 |
|---|---|
| 賠償責任特約 | ペットが他人や物に損害を与えるなどにより、飼い主に法律上の賠償責任が発生した時、所定の保険金が支払われる。 |
| 火葬費用特約 | ペットが死亡した際、火葬や埋葬を行った時に所定の保険金が支払われる。 |
| 健康診断サービス | ペットの健康診断サービスを受けることができる。 |
| 獣医師サポート | 電話などで獣医師のサポートを受けることができる。 |
| 多頭割引 | 複数のペットが保険に加入する場合、契約数に応じて一匹当たりの保険料が割引になる。 |
ペット保険が必要かどうかを判断する
ペット保険は掛け捨ての保険のため、ペットがずっと健康であればその分の保険料が手元から消えるだけという見方もできます。しかし、貯金で備えるのであればペットがずっと健康な場合は手元にその分のお金が貯まることになります。ペット保険で支払う保険料をペット用の医療費として貯金しておくという方法をとっている人もいるでしょう。ペット保険は年齢制限があったり、既往症は補償対象外になるなどの面があるためペットが健康で若いうちに加入の有無を選択することが望ましいです。ペット保険のメリット、デメリットを踏まえてペット保険に加入するかどうかを判断しましょう。
ペット保険と貯蓄どちらで備える?
ペットが将来、ケガや病気になってしまった時に必要となるかもしれない医療費を飼い主としてどのように準備するか、という事はペットを飼うときに必要な準備として考えておく必要があります。ペットを飼った時に必要になるかもしれない医療費は貯蓄で備えようと考えていても貯蓄が十分に貯まる前に大きなケガや病気をしてしまい医療費がかかる事があります。また、定期的な通院などが増え貯蓄分では足りないことや、ペットの医療費用とためておいた貯蓄を別用途で使ってしまい、いざ、というときに困ってしまう事も考えられます。貯蓄で医療費を補填する場合、定期的な通院や高額な医療費が必要になってもペットに十分な医療を受けさせてあげられる資金的な余裕があるかどうかという事も考えペット保険の加入を検討しましょう。
- 十分に貯まる前に高額な医療費がかかる事がある
- 貯蓄分で足りない可能性がある
- 別用途で使ってしまう可能性がある
まとめ
ペット保険は公的な医療保険がないため、ペットにかかった医療費は飼い主が全額自己負担する必要があります。そういったペットの医療費負担に備えるためにペット保険がありますが、ペット保険に加入していても自己負担が必要であったり、補償とならないケースがあったりします。しかし、人も健康保険制度がありますが、病院でかかった医療費は3割負担で自己負担分はありますし、自由診療で診察を受ければ健康保険が使えません。民間の医療保険もしてもらいたい保障の商品に保険料を支払って加入します。ペット保険も同じように考え、飼い主が家族の一員であるペットのために加入が必要かどうか選択しましょう。